|
「見る」ということの中には、眼球運動の未発達から形態知覚だけ
でなく、ものを識別したり、まねたり、奥行きを計ったり、といったこ
とも含まれます。発達 障害をもつ子ども達の中には、視覚的注意
の持続が難しくなり、移動や姿勢変換そして遊びや学習、日常生
活に影響を及ぼしてしまう子どもが多く、見ているよ うなのに実は
見えていなかったり、ものを探すのがとても下手だったり、という子
がいます。具体的な対応が難しいこのような状態を、視力に問題が
なく見え方 に問題のある子ども達に対して、ひとりひとりのお子さん
の特性や発達段階に応じて発達の援助を行なうと共に、注意を維
持しながら姿勢コントロールと視知覚 や体性感覚などの感覚情報
を組み合わせ、同時に遊びやADL(日常生活動作)につなげるた
めに視覚機能の検査、ものの見え方に対する援助を行なってい
ます。
【M.Mさん 小学1年生】
・ 見る時に左目を前に右目を後ろにしたように顔を傾ける。
・ 近くを見る時に顔を近づける。
・ 文字を覚えることが苦手。
・ 読んでいるところがわからなくなったり、行を飛ばすことがある。
・ 探し物を上手く見つけられない。
検査の結果
・ 眼球の動きが乏しく、追視・輻輳などに問題がみられる。
・ 追視・サッケードでは頭との分離が難しく、気が散りやすく、姿勢保持が難しい。
・ 図地判別や図形をイメージすること、記憶は苦手。
・ 視覚システムの発達に影響を与える原始反射の残存があり、目に見えたもの
に引きずられて姿勢が崩れやすくバランス感覚も悪く、左右の認識が不十分。
トレーニングの内容と期間
療育センターで月に1回の作業療法(リハビリテーション)の訓練の中で各種トレ
ーニングを続け1年間経過観察を行ないました。現在では普通級と個別支援級
に通われ、黒板の文字を写すのが苦手であったり、ノートを途中から書き出した
り、同じページにいろいろな教科を書き写したりとノートをうまく使えなかった り、
気が散りやすく、集団の一斉指示に従えない状況はありますが、眼球運動の改
善に伴い、苦手な課題に取り組もうという意欲が顕著に見られるようになって き
ました。空間の中にある物を数えられるようになり、書くことへの抵抗がなくなり、
音読するときに、1文字ずつ途切れ何を読んでいるかわからなかった状態 から、
文節ごとに読めるようになってきました。
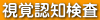 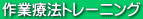 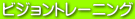 |

